京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。
 金田歯科医院
金田歯科医院
 金田歯科医院
金田歯科医院
MENU
09:15〜13:00(最終受付12:00)
14:30〜18:15(最終受付17:45)

公開日:
目次
こんにちは。京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」です。

毎日行う歯磨きを「なんとなく」行なっている方も多いのではないでしょうか。正しい歯磨きは、虫歯を予防するために必要不可欠です。
ここでは、歯磨きの正しい方法やポイント、歯ブラシの選び方までわかりやすく解説します。ぜひ参考にして、正しい歯磨きの知識を身につけ、虫歯予防につなげてください。

歯磨きの回数はできれば一日3回以上が理想的といわれています。一日3食、毎食後に歯磨きをすることを想定して3回としています。回数は、その人のライフスタイルによって変わりますが、大切なのは回数ではなく、歯磨きをするタイミングです。
お口の状態に対して「食後=汚れている」というイメージをもっている方は多く、食後の歯磨きが習慣化していることが多いです。食後は、食べカスや糖質の付着でお口が汚れているため、毎食後に歯磨きをすることが大切だといえます。
あまり知られていないのが、就寝前と起床後の歯磨きの重要性です。
「寝るだけなのにどうして歯磨きをしないといけないのか」と感じる方もいるでしょう。就寝中は、起きている時と比較すると唾液分泌が減少します。唾液が減ると、お口の中が乾燥した状態となり、菌が繁殖しやすくなります。そのため、就寝前と起床後に歯磨きをすることが大切なのです。特に、起床後は一日の中でお口が最も汚い状態なので、しっかり歯磨きをしてから食事をとりましょう。

歯磨きの回数やタイミングについて説明しました。
次に、一回の歯磨きでしっかり汚れをリセットできるよう、正しい歯磨きの方法について磨き方ごとに説明します。
スクラビング法とは、歯や歯肉に対して毛先を90度の角度であて、左右に小刻みに動かし、歯を1本ずつ磨く方法です。毛先は軽くあて、優しく磨きます。歯間部分も磨くと、歯垢の除去に効果的です。強い力で磨くと歯肉を傷つけてしまう原因となりますので、小刻みに優しい力で磨くことが大切です。
スクラビング法は、比較的簡単で「歯磨きの基本的な磨き方」といわれています。
バス法とは、歯と歯肉の間に毛先を45度の角度であて、左右に小刻みに動かし1本ずつ磨く方法です。小刻みに優しく行うことで、歯周ポケット内の歯垢の除去だけでなく、歯肉のマッサージにもつながります。バス法も、強い力で磨いてしまうと歯肉を傷つけてしまうので注意しましょう。
ローリング法とは、歯肉から歯の先に向け、歯ブラシを回転させるように磨く方法です。従来は虫歯予防によいといわれていましたが、現代では磨き残しも多く、虫歯予防の観点からあまり推奨されていません。
フォーンズ法とは、毛先を歯や歯肉に対して90度の角度であて、回転させながら磨く方法です。歯間部分に磨き残しがあるため、他の磨き方と組み合わせることが大切です。あまり力が必要ないため、お子さまや高齢の方に向いている磨き方といえます。

歯磨きをするうえで大切なポイントを、詳しく解説します。
「虫歯予防にはフッ素が大切」という話を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。フッ素は、歯の表面にあるエナメル質を強くし、虫歯菌の働きを抑制するため、虫歯予防に大切だといわれています。
虫歯になりやすい乳歯の時期から大人まで、フッ素をなるべく長く歯に残すことが大切です。フッ素は、歯磨きをしてうがいをしたあとも、しばらくお口の中に残ります。そのため、毎日使用する歯磨き粉はフッ素配合のものを選択しましょう。
歯ブラシのほかに、歯間ブラシやフロスを使用すると、歯垢の除去率があがるといわれています。歯ブラシだけでは取り切れない歯間部分の汚れを取りのぞいてくれるので、毎日使用する習慣をつけることが大切です。
すき間が大きい部分は歯間ブラシ、すき間が小さい部分はフロスや糸ようじを使用するなど、部位によって選択していくと、より効果的に汚れを落とせるので、ぜひやってみてください。

さまざまな種類がある歯ブラシですが、皆さんはどのように歯ブラシを選んでいますか。毎日使用するため、自分に合った歯ブラシを使用することが大切です。
歯ブラシを購入するときに注意してほしいポイントを、解説します。
歯ブラシの毛の硬さは「やわらかめ」「ふつう」「かため」にわけられています。ドラッグストアで選ぶとき、なんとなく選んでいる方も多いでしょう。
「かため」は、汚れが一番落ちやすいですが、毛先が硬いため歯や歯肉を傷つけてしまうリスクがあります。「かため」は、力が入れにくい高齢の方などに向いているでしょう。
「ふつう」は、毛先が適度な硬さで汚れをしっかり落とせるため、幅広い方に向いています。お口のトラブルがなく、健康な方は「ふつう」を選択するとよいでしょう。
「やわらかめ」は、一番汚れが落ちにくいといわれていますが、歯や歯肉を傷つける心配がありません。歯肉炎など、お口のトラブルがある方に向いているでしょう。
毛先の形状には「フラット型」と「山型」があります。
「フラット型」は、毛先が平らになっている凹凸のない形状です。歯並びに問題がない方は、フラット型を選択すると歯垢を落としやすく、角を使用することで細かい部分もきれいにすることができます。
「山型」は、山のような凹凸がある形状です。歯並びに問題があり、フラット型では凹凸部分が磨きにくい場合、山型を選択すると凹凸部分にも毛先がフィットして、歯垢が落としやすくなります。
ヘッドの大きさを選択する目安となるのが、上の前歯2本分の幅の大きさです。「大きめ」と「小さめ」にわけられているので、自分の歯に合う大きさを選択しましょう。
歯並びが複雑の場合は「小さめ」を選択することで、凹凸部分の汚れを落としやすくなります。力がなく、小刻みに1本ずつ磨くのが難しい方は「大きめ」を選択すると、効果的に歯磨きができます。
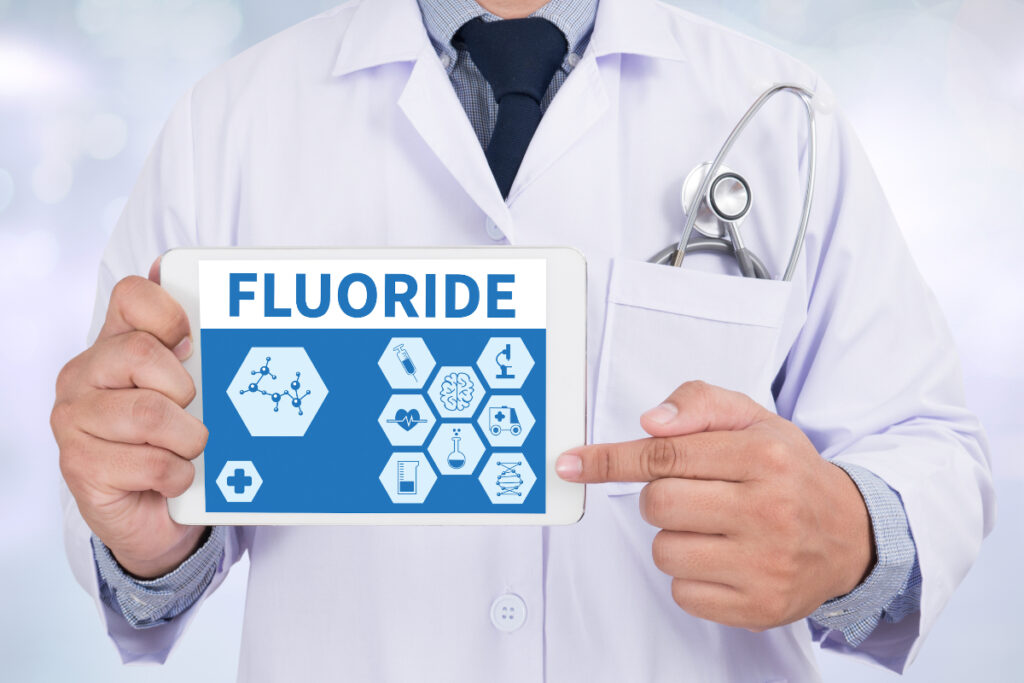
毎日の歯磨きでフッ素を使用することも大切ですが、それに合わせて歯医者でフッ素塗布をしてもらうと、より効果的にお口の中にフッ素を残すことができます。
お子さまから高齢の方まで、すべての方の虫歯予防として、歯科医院でのフッ素塗布は推奨されています。1回のフッ素塗布は500~3,000円と、比較的安価で受けられ、痛みや副作用の心配もないためおすすめです。
1回塗布すると、3~4か月程度は効果が持続します。

「毎日しっかり歯磨きをしているのに虫歯ができた……」と、ショックを受けることもあるかもしれません。歯磨きをしっかりしても、防ぐことのできない虫歯もあるのです。
なぜ歯磨きをしても虫歯ができてしまうのでしょうか。詳しく解説します。
唾液の分泌が少ない方は、お口の中が乾燥することで虫歯菌が繁殖しやすくなります。また、唾液には自浄作用があり、お口をきれいに保つ効果がありますが、分泌が減ることでその効果が薄れ、虫歯になりやすくなります。
唾液が少なくなる原因は、なんらかの疾患が隠れていることもあるので、心当たりがある方は歯科医師へ相談してみるとよいでしょう。
糖分ばかり摂取すると、虫歯菌が増殖して虫歯形成につながります。また、食生活が乱れ栄養が偏ることで、歯の質が悪くなり、虫歯になりやすい歯となります。
虫歯菌が喜ぶ食生活をしていないか、見直すことが大切です。

今回は、歯磨きによる虫歯予防について説明しました。毎日正しい歯磨きをすることで、虫歯予防につなげることができます。虫歯のない快適な生活を送れるよう、毎日の歯磨きを大切にしましょう。
歯磨きによる虫歯予防についてお悩みの方は、京都市左京区岩倉の歯医者「金田歯科医院」にお気軽にご相談ください。